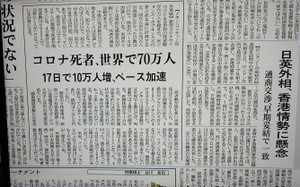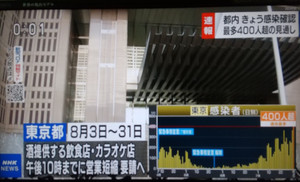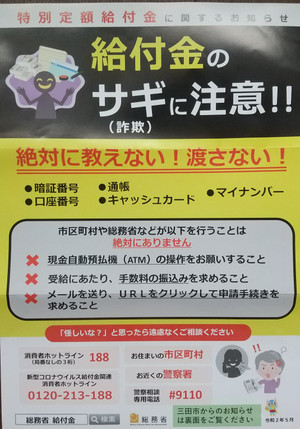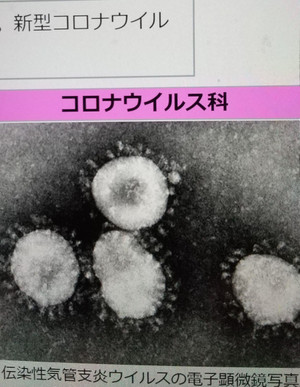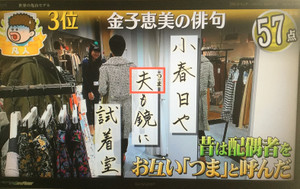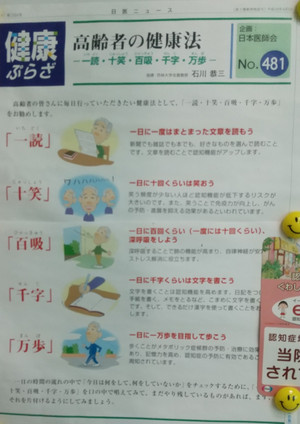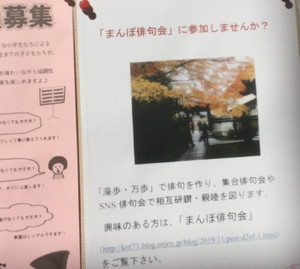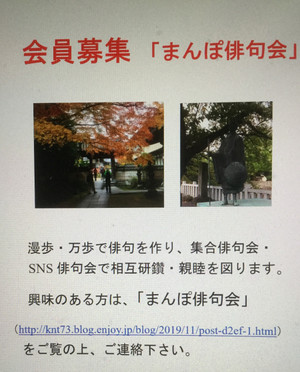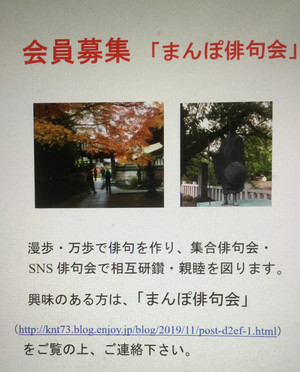芭蕉の含蓄のある俳句の翻訳についてご理解を頂くために注釈を付記しました。英語俳句(HAIKU)作成の参考にも役立てば幸いです。
(51)
稲雀茶の木畠や逃げどころ
(ina-suzume chanoki-batake-ya nigedokoro)
(A)
rice-field sparrows_
a tea field is
their escape place
(B)
sparrows in the rice-field
escaped into
a tea field
(注)
芭蕉のこの俳句は三段切れです。「や」を「は」とか「が」にすると散文的・説明的になるのを嫌ったのかも知れませんが、「茶畠は良い隠れ場所だな」という詠嘆を「や」で表現した結果三段切れになったに過ぎないでしょう。「三段切れでも意味が分かれば構わない」という例句になります。
英語のHAIKUとしては単語を羅列するだけでは詩的でなく意味不明瞭になるので動詞を補って翻訳しましたが、(A)の方が(B)より俳句らしいでしょう。
(52)
草の戸をしれや穂蓼に唐がらし
(kusa-no-to-o shire-ya hotade-ni tōgarashi)
(A)
be aware of the grass door_
buckwheats in ear
and red peppers
(B)
be aware of the grass door_
water peppers in ear
and red peppers
(注)
この俳句は芭蕉の草庵に来る客への歓迎句です。
「蓼」の英訳には、buckwheat(そば)やjoint grass(紀州雀ひえ)、water pepper(柳蓼)などありますが、(B)の方がred pepperとの釣合が良いかもしれません。
(53)
牛べやに蚊の聲よはし秋の風
(ushi-beya-ni ka-no-koe yowashi aki-no-kaze)
(A)
in the cow room
feeble hums of mosquitoes
autumnal wind
(B)
in the cow room
a feeble sound of mosquito
autumnal wind
(注)
この俳句は牛が小屋でなく人家の土間にある牛部屋で飼われているのを詠んだものでしょう。蚊は沢山居たでしょうから、(A)のように複数にする方が適訳だと思いますが、晩秋の残り蚊だとすると(B)の単数の方が良いでしょう。
なお、一般に、前置詞を使い過ぎると散文的になるのでなるべく省略する方が良いのですが、この句の場合は助詞「に」対応する「in」を省略すると、作者も牛部屋に居るニュアンスになり、誤訳になるでしょう。
(54)
波の間や子貝にまじる萩の塵
(nami-no-ma-ya kogai-ni-majiru hagi-no-chiri)
(A)
between sea waves_
bush-clover trashes
among small shell-fishes
(B)
between shore waves_
bush-clover trashes
among small shells
(注)
(A) は「小貝」を「生きた貝」の意味に解釈した英訳です。
(B) は「小貝」を「貝殻」と解釈し、「波が浜辺の波」であることを明瞭にし、「shore waves」と意訳して「韻」を踏んでいます。
芭蕉はそのような区別は意識せず、「貝と萩の花片との対比」に興味を抱きこの俳句を詠んだのでしょうか。
いずれにせよ、英語HAIKUとしては(B)の方が適訳でしょう。
(55)
海士の屋は小海老にまじるいとど哉
(ama-no-ya-wa koebi-ni majiru itodo-kana)
a fisherman’s hut_
among shrimps
a camel cricket
(56)
身にしみて大根からし秋の風
(mi-ni-shimite daikon-karashi aki-no-kaze)
penetrating my body_
the radish bitterness,
an autumnal wind,
(57)
芭蕉野分して盥に雨を聞夜かな
(basho-nowaki-shite tarai-ni-ame-o kiku-yo-kana)
(A)
the typhoon against banana trees_
rain drops into a tub,
the sound in the night
(B)
banana trees in the typhoon_
the sound of rain on a water tub
in the night
(注)
(A)では台風に重点を置き、「(昼間は眺めていたが)夜は雨音を聞いている」ことを詠んだと解釈し、(B)では、バナナの木に視点を置いて「夜によく聞こえる雨音を聞いている」と解釈し、ニュアンスを変えて翻訳しました。夜通し雨音がしている情景を詠んだとすれば、「in the night」は「(all) through the night」にすると良いでしょう。いずれにせよ、(B)の方が原句の句意に近い適訳だと思います。
(58)
わせの香や分入右は有磯海
(wase-no-ka-ya wakeiru-migi-wa ariso-umi)
(A)
the scent of early rice_
on the right side of my going way,
rough surf beach
(B)
the early-rice smells_
on the right side of my path
Arisoumi
(注)
(A)では「有磯海」を意訳し、(B)では固有名詞としてそのまま表現しました。なお、一般に、俳句ではなるべく動詞を省略する方が簡潔で良いと思いますが、この句の「わせの香」は(B)のように動詞で表現する方が生き生きして良いように思います。
ちなみに、「奥の細道」や「私の芭蕉紀行」というサイトに参考になる記事があります。青色文字をタップしてご覧下さい。
(59)
賤のこやいね摺掛けて月をみる
(shizu-no-koya ine-surikakete tsuki-o-miru)
(A)
the peasant’s child_
upon beginning to hull rice,
looks up at the moon
(B)
the humble boy
began hulling rice,
looked up at the moon
(注)
(A)は芭蕉の心象風景か、現に見ている情景か、いずれにせよ「みる」をそのまま現在形に英訳しましたが、英詩のHAIKUとして何だか嘘っぽく不安定な感じがします。
(B)は芭蕉が見た情景を詠んだものとして英訳しました。散文的になるのを避けるために、「then」とか「and」を省略しています。(A)も「upon」を省略する方がHAIKUとして適訳になるでしょうが、(B)のように過去形で表現する方が英詩として実感があり安定感があります。
「英語の俳句は現在形で表現すべきである」と誰かが言っていましたが、それは俳句に対する誤った認識でしょう。
(60)
荒海や佐渡によこたふ天河
(araumi- ya sado-ni-yokotau ama-no-kawa)
(A)
the rough sea_
lying over to Sado,
the milky way
(B)
the wild sea
lying against Sado_
the milky way
(注)
この俳句は芭蕉が実際に見て詠んだものではなく、心象風景を詠んだもであると一般に言われています、「よこたふ」の主体が何かについても議論の余地があるようです。
(A)は通説どおり「天河がよこたふ」と解釈した英訳であり、(B)は「荒海がよこたふ」と解釈した翻訳です。
(B)は「や」を切れ字ではなく詠嘆と捉える読み方をしたもので、三段切れの読み方でやや無理が生じます。
しかし、芭蕉は上記(51)のように「や」が詠嘆的に主体を表す三段切れの俳句を他にも作っていますので、(B)の解釈を無下に否定することは出来ないでしょう。