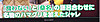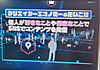老ひたれば無欲の牛歩去年今年
(oitareba muyoku-no gyu-ho kozo-kotoshi)
(薫風士 Kunpūshi)
resigned to unselfish old age,
steadily by ox-like steps_
kozo-kotoshi
(translated by L.P. Lovee)
(Note)
“kozo-kotoshi” literally means “last-year this-year”, which means a time between a new year and the last year.
月雪とのさばりけらし年の暮
(tsuki-yuki-to nosabari-kerashi toshi-no-kure)
(芭蕉 Bashō)
moon and snow_
festively fleeting,
the end of year
(translated by L.P. Lovee)
去年今年貫く棒の如きもの
(kozokotoshi tsuranuku bōnogotoki-mono)
(虚子 Kyoshi)
(translated by L.P. Lavee in the following three ways:
(A)
Kozokotoshi_
something just like
a piercing-stick
(B)
time pierces
kozokotoshi
like a stick
(C)
my belief in haiku
pierces kozokotoshi
like a stick
(Note)
(A)is a substantially literal translation.
(B)is a translation based on a conventional way of interpretation.
(C)is a translation according to a new interpretation of L.P. Lovee.
HAIKU is AI: not Artificial Intelligence, but Art of Intelligence, leading to "LOVE" 「愛」.
Haiku Aids Increasing Knowledge Universally.
Click here to see Kyoshi 's 100 haiku.
Click nere and see "虚子100句英訳をHIAホームページでご覧下さい。"
Click here and see "俳句・HAIKU by L. P. Lovee (9) 《去年今年・kozokotoshi》"
Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.