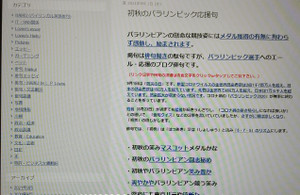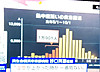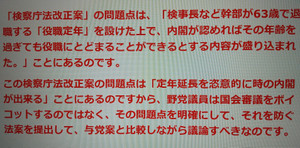《初仕事・仕事始・出初》能登半島地震緊急支援にオスプレイを!
被災された方々に、
謹んでお見舞い申し上げます。
この記事のタイトルを見ただけで馬鹿扱いにせず、最後まで読んで頂けると幸いです。
NHKテレビの「あさイチ」で、黒柳徹子さんと朝ドラ「ブギウギ」のモデルになった淡谷のり子との往年の対談シーンが先日放映されましたが、淡谷のり子の歌を聴いて16歳で特攻隊員として飛び立った戦時下の至誠のある青年のことを思うと、日本と世界の平和の為にもっと若い政治家が奮起して活躍してほしいという切望を新たにしました。
軍事独裁政権が、天皇を現人神(あらひとがみ)にして太平洋戦争を推進し、有無を言わせず、純真な若者を戦争に駆り立てた悲壮な一時期がありましたが、かっての政治家や官僚などはそれなりの倫理観を持っていたと思います。
しかし、日本社会の活性化や政治の刷新の為には、長老の偏狭さが老害になっていないか派閥の幹部は謙虚に考えて、若者に活躍の場を譲る配慮をして欲しいものです。
政治資金規正法違反の多額のキックバックを受け取って真面に税金も払っていない倫理観のない議員がいる現状は悲しいことです。
「政策研鑽の場とし派閥が必要だ」と言っている長老がいますが、若者の人材育成にはかっての狭い村社会的な派閥に依存するのではなく、全体的な人材育成の場を設けて、複雑多様な国際社会に適応出来る視野の広い有為の人材を育成すべきでしょう。
(写真)
4ch-TV画面の一部分
派閥解消に反対している料簡の狭い長老が居座り、老害になっては困ります。
令和の政治家や官僚には21世紀に相応しい倫理観と哲学を持ってほしいものですが、龍が昇らないままに大年を迎えることにならないように、起死回生の政界刷新・若返りが推進されることを切望しています。
初仕事思ひを込めて句を口に
頼もしき消防隊や出初式
寒に入る心ばかりの義援して
「違うな」は「たがうな」と読んで下さい。
自民党の刷新は、「岸田下ろし」を口にしている長老が引退すれば足かせが無くなり、岸田総理が国民の納得できる思い切った若返り組閣人事をすれば、容易に実現出来るでしょう?
拙句(「起死と岸」のゴロ合わせのダジャレ川柳)に込めた思いを実現すべく、俳句HAIKU をフォローしてリンク記事をご覧頂き、シェアして頂けると幸いです。
NHKのニュースを見ていると、能登半島地震の被災地で石川県に土砂崩れなどの影響で孤立している地域があるようです。
自衛隊の救援物資を運ぶ予定の海保機に日航機が衝突するという不幸な事故が起こりました。
オスプレイは米軍や自衛隊基地に現在30機程(?)あるようですが、屋久島沖に於ける米軍機の墜落事故の結果、全て飛行停止になっています。
米軍オスプレイの墜落事故は軍事訓練目的の無理な飛行をしたからではないのでしょうか?
機体の問題点を把握して、安全第一の飛行をすれば、オスプレイを能登半島地震の被災地の救援物資の運搬などに活用出来るのではないでしょうか?
日本はオスプレイを十数機買ったようですが、オスプレイは一機の価格が200億円(?)もするのにそんな簡単なことも出来ないほどお粗末なオスプレイを買ったのなら国民が払った貴重な税金の3000億円(?)もの無駄使いをしていることになります。
関係者がまだ未検討なら、大至急、聞く耳を持つ岸田首相には税金の有効活用を検討して将来の災害対策の布石として、将来の大災害の救助にオスプレイを活用することも非常事態の緊急処置として是非とも検討して頂きたいと思いますが、維持費と安全性の観点でオスプレイの使用は検討に値しないということでしょうか?
自民党の安倍派議員などが政治資金規正法違反容疑で逮捕され、自民党や岸田内閣の支持率が最悪のレベルに低下しています。
「あらゆる可能性を排除せず」真に国民のためになる思い切った決断をして政治の刷新・若返りを推進しなければ、岸田内閣が「万事休す!」になるのは時間の問題ではないでしょうか ⁉️
「難を転じて福となす」
ピンチは最大のチャンスです。
岸田内閣やオスプレイの起死回生の活躍を期待して駄句を口遊みました。
オスプレイ平和の使途の初仕事
オスプレイ仕事始めに石川へ
オスプレイ天に昇るや龍の如
掲句は季語「龍淵に潜む」と「龍天に昇る」を捩った俳句擬きの比喩の拙句です。
「初夢の俳句」をご覧下さい❗
(薫風士)
最新の俳句や英語俳句の記事は、青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップしてご覧下さい。