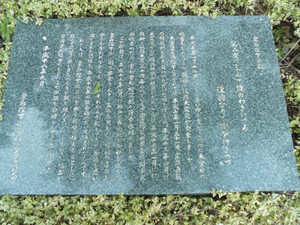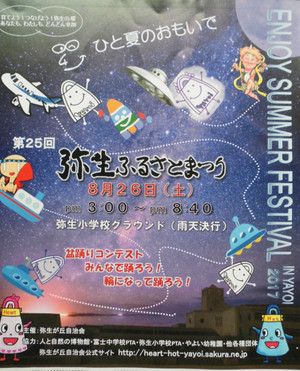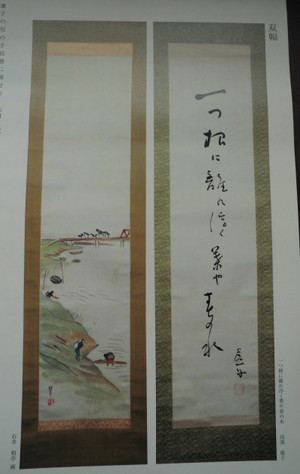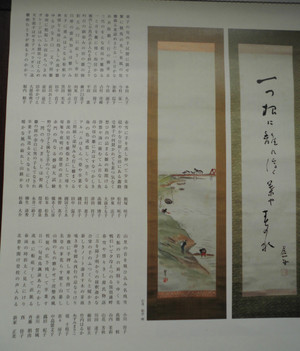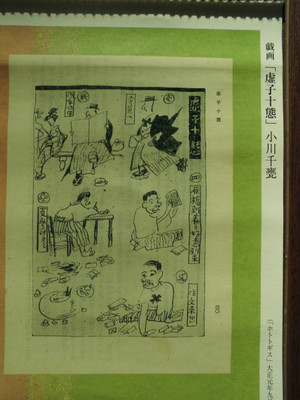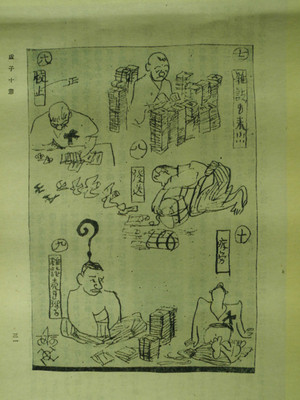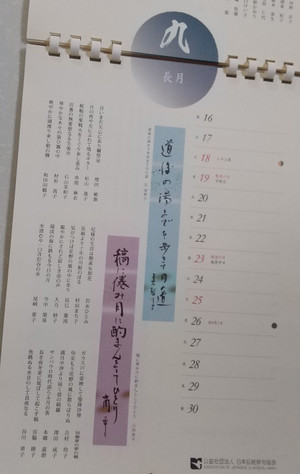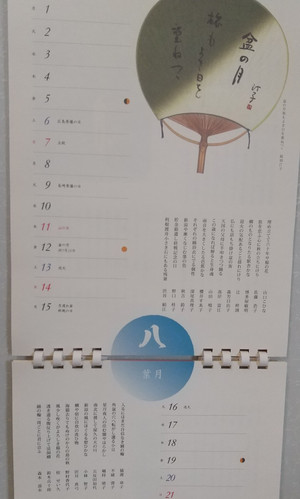(2025.3.19 更新)

この写真は、NHK-TV 二ュ-スの一画面ですから、この画面だけを見て誤解しないで下さいね。
トランプ大統領は、日米安保条約について、「我々は日本を守らなければならないが、日本は我々を守る必要が無いのは不公平だ」と言っていますが、日本は太平洋戦争で多大の犠牲を払って、世界の唯一の原爆被爆国として米国の主導した連合軍の要求を受けて戦争放棄の新憲法を制定していますから、「この平和憲法に基づき平和を守ることによって日本は米国に対して公平な対応をしている」と言えるでしょう。
世界の人々がこの正しい認識に共感して、「日本の平和憲法の精神を国是として、世界平和の為の市民運動を推進してくれること」を切望しています。
ロシア軍のウクライナ侵攻によって、多大の犠牲者が生じています。
プーチン大統領の侵略政策は決して許すべきではありません。
経済的制裁の悪影響は世界に広がっており、持久戦に耐える覚悟が必要ですが、この事態は持久戦に耐えることでは済まないかもしれません。
独裁者も人間ですから、独裁政治家が短気を起こすと世界はどうなるか心配なことです。
「太陽と北風」の寓話を馬鹿にしないで、世界の人々が平和運動を推進してくれることを切望しています。
青色文字をクリック(タップ)して、「梅東風や届け世界にこの思ひ」や「血に染むなドニエプルてふ春の川」に書いた思いを一読し、シェアして頂ければ望外の喜びです。
(2015.5.10 の記事)
4月29日は「昭和の日」である。
歳時記の「憲法記念日」には山田弘子の俳句「国旗立つ憲法記念日のパン屋」など66句リストされている。
先日、東京新聞の「平和の俳句」募集に応募した友人の入選句のことなどを「俳句談義(14):俳句の片言性と二面性」に書いたが、友人が東京新聞のコピーを郵送してくれたので入選した俳句とコメントの中で特に印象に残った二つを次に転載させて頂く。
「青春の昭和切なし鰯雲」 斎藤けい(90)横浜市
昭和19年、兄は二度目の招集で南方へ、将来を約束した一つ違いの幼なじみは中国大陸へ出征した。終戦になっても二人はなかなか帰らず、鰯雲の浮かぶ秋空を見上げながら待ち続けた。終戦翌年の秋、兄は半袖の軍服にぼろぼろの靴を履いて、夜、人目を忍ぶように裏口から帰ってきたが、半年は放心状態だった。幼なじみは小さな箱になって戻ったが、中は石や砂だった。
上記コメントの最後にある「石や砂」は「本との出会い(2)」に書いたエッセイ集「尾曲がり猫と擦り猫と」の「石ころ」と同じである。
小学生(国民学校初等科)の頃、戦死者が級友のご家族だった場合だろうが、遺骨を白布に包んだ箱を胸に下げてご遺族の方が帰って来られるのを駅まで迎えに行ったことがある。遺骨だと思って恭しく頭を下げていたが、石ころであることが多かったのだろう。
「夏の高校野球」で「甲子園の砂」を球児が袋に詰めるニュースをよく見かける。感慨無量である。
「ウイキメディア」によると、「1941年 - 1945年」の大会は太平洋戦争のため取り止めになっている(1941年の第27回の回次は残る)。
お手玉の小豆で赤飯父はゆく 桜井義男(80)東京都
戦争中、もらった砂糖でお汁粉を作るため、姉二人のお手玉から小豆を取り出した。
二人は東京大空襲の夜にはぐれ、遺体も見つからなかったが、最後にお手玉をした姿を今も覚えている。友人の家もお手玉の小豆で赤飯を炊き、父親の出征を祝ったが、帰ってこなかったという。(以下省略)」
このブログを書いていて、「欲しがりません勝までは」ということが当たり前だったのか、無いことが分かっていたからか、特に強いられることもなく、ひもじいのを子供心に我慢をしていたことを思いだし、こみあげてくる感情に我知らず涙ぐんでしまった。
「もったいない」という気持ちは現在でも強く感ずる。
当時は食べ物があれば何でも有難く食べるのが当然だった。
現在は飽食の時代で、子供が食事の好き嫌いをするのが当然になっている。
だが、食物アレルギーということもあるので、食べることを無理強い出来ない。
火の奥に牡丹崩るるさまを見つ
(加藤楸邨)
この句は大空襲で自宅が燃え崩れる様子を詠んだものであることは前書きで一応理解できるが、真の句意はわからない。
楸邨の言いたかったことは何か?
大牧広氏は「楸邨が国民の呻きを牡丹に託したもの」であると解釈し、次のように述べている(抜粋)。
この「火」は当然焼夷弾による炎上させられた火である。紅連の炎の中に崩れてゆく牡丹、もしこれが人であったらこの世の最後の悲鳴を挙げたであろう。それも叶わず黙って焼かれていった牡丹、私はこの牡丹を作者が人間をイメージして詠んだような気がしてならない。何の罪もない一般国民があの忌わしい業火の中で命を落さなければならなかった時代。この国民の呻きを牡丹に託して詠んだと思えてならない。
気の向くままにインターネットで検索していると、「思考の部屋」というサイトの「94歳の荒凡夫~俳人金子兜太の気骨~」という記事に兜太の次の俳句があった。
水脈の果炎天の墓碑を置きて去る
津波のあと老女生きてあり死なぬ
「津波」の句は老女の生命力の逞しさを讃えているのだろうが、「貴重な若者の命は奪われたが老女はまだ生きている」という自然の不条理を皮肉を込めて表現していると解釈できないこともない。
日経新聞WEB刊を見ていると日米首脳会談の夕食会でオバマ大統領が次のような自作の俳句を披露している。
「春緑 日米友好 和やかに(Spring, green and friendship/United States and Japan/Nagoyaka ni.)」
オバマさんが「和やかに」と日本語を使ったのは親日・友好の意を表す意味もあったのだろうが、「和やか」は含蓄のある言葉でぴったり対応する英語が無いからでもあろう。
国際俳句協会では「俳句」が世界文化遺産に登録されるように努力しているが、俳句には言葉の壁があるので世界遺産登録は「和食」のように簡単ではない。
高浜虚子は終戦に際して次の句を作っている。
秋蝉も泣き蓑虫も泣くのみぞ
「敵といふもの今は無し秋の月」「黎明を思ひ軒端の秋簾見る」と併せて読むと、「秋蝉も蓑虫も泣くのみだ。泣きたいものは思いぞんぶん泣けばよい。だが、自分は泣かない。終戦になって、自由に句作が出来る。さあこれから本番だ。」と清々した気持ちで詠んだ句だと思う。
虚子は「亀鳴くや皆愚かなる村のもの」という句を作っている。
明治時代に作った俳句らしいが、人を食った句である。
句作の背景や経緯を知らなければ真の句意は不明である。
この句が作られた「場」をご存知の方があれば是非教えて頂きたい。
「皆」とは誰を指すのか? 「村」とはどこのことか?
「もの」とは「者」と「物」のいずれを意味するのか?
「亀」は「虚子」の比喩でないか?
単に文字通りのことを客観写生したのだろうか?
たとえば、「どこかの村で俳句会を催し、集まってきた者は碌な俳句も出来ない愚か者だった」という句だろうか?
「『花鳥諷詠の心』を知らぬ者は愚かだ」と言っているのだろうか?
「自分を含めて人は皆愚かな者だ」と嘆いているのだろうか?
「村」とは「日本の村社会性」の比喩ではないか?
「戦争推進者は皆愚か者だ」と比喩的に詠んだ句ではないか?
いずれにせよ、さまざまな解釈が可能である。
虚子は「深は新なり」と言っている。穿ちすぎかもしれないが、句意が不明だということは、「しっかり考えよ」と謎をかけていると解釈できないこともない。
昔は人災にしろ、自然災害にしろ、慟哭するしか仕方がなかっただろう。
だが、現在は科学技術も進歩しており、民主主義の時代である。
災害の防止や抑制は努力次第で不可能ではない。まして、戦争は叡智を集めて未然に防ぐ努力をすべきである。
独裁政治、覇権主義、軍事力の増大と情報非公開による国際的不信、貧富の格差拡大、一方的な道徳観の押し付け、国家間の利害対立、ナショナリズム、等、戦争発生の要因は多多あるが、このような要因の発生を防止・除去することは可能である。
国際貿易や文化交流を深めて、相互理解・相互依存を高めることが平和の維持・戦争の防止につながる。各国がその努力をすることが必要である。
日本政府が注力すべきことはそういうことを世界の指導者に働きかけることだろう。
法律の条文は俳句のように如何様にでも解釈できる笊法であってはならない。
憲法の拡大解釈による自衛権の行使が、憲法改正後に時の政府の条文解釈次第で更に拡大されるようになってはならない。
現憲法だからこそ明文にない自衛権の拡大解釈に歯止めがかかっている。
憲法が改正されるとその歯止めが無くなり、更に拡大解釈をされる恐れがある。
現憲法に不備があるというなら、その不備を逐一吟味し、拡大解釈が出来ないことを明確にして、国民が納得できるように討議する場を設けるべきだろう。
大切なことは総論のみならず各論である。
自民党の改正条文草案に限らず、野党の改正案があればそれも含めて、法律学者・憲法学者、政治家、評論家が時間をかけて真剣に議論し、公開すべきだろう。
公共機関は憲法記念日など祝日の行事をする場合には国旗を掲揚するが、一般の家庭で国旗を掲げている家はほとんど見かけない。

日章旗が、平和国家のシンボルとして内外で何らの抵抗なしに受け入れられ、掲揚される日は来るのだろうか?
青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。