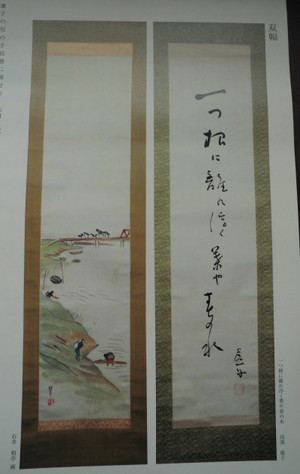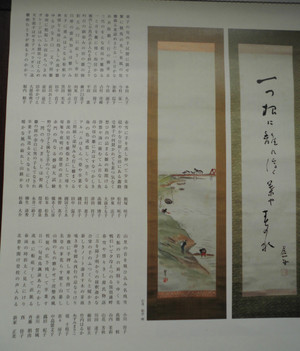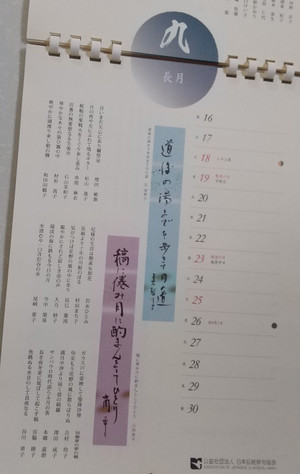4月8日は高浜虚子の命日「椿寿忌」です。
日本気象協会の「桜開花情報」によると北海道・東北地方・北陸地方以外の都府県では満開です。
桜・花の俳句と写真を集めました(ここをクリックしてご覧下さい)。
(青色文字をクリックすると関連の記事がご覧になれます。)
ご覧の写真のようにチュヌの散歩道の桜も満開になりました。
この週末は雨模様でしたが、花見でお疲れの方も居られるでしょう。
そこで、高浜虚子の掲句「花疲れ眠れる人に凭り眠る」の英訳にチャレンジしてみます。
俳句の英訳をするにはその作者が句を詠んだ背景を考え、原句の句意を訳出する必要があります。俳句はその解釈を読者の想像にゆだねる特徴があります。日本語の情緒的な表現・ニュアンスを英語HAIKKUに訳出することは至難です。英語は論理的な構文が特徴ですから、俳句で省略される主語など、英語では省略することが出来ません。したがって、原句が詠まれた情景を考えて、省略された主語を補って英語のHAIKUにしなければなりません。
掲句の場合は少なくとも次の三通りの情景が考えられます。
(A) 眠っている人に虚子がつい寄り掛かってうとうとした。
(B) うとうと眠っている虚子に隣の人が寄り掛かってうとうとした。
(C) 互いに寄りかかってうとうとしている二人連れを虚子が見た。
虚子に寄り掛かったのはうら若い女性か、むさくるしい男か?
二人連れは若者か、老夫婦か、恋人同士か?
様々な情景が思い浮かびます。俳句鑑賞の楽しさ、面白さです。
俳句は「省略の文学」といわれますが、「花疲れ眠れる人に凭り眠る」も主語が省略されています。英語では主語の省略はできませんので、先ず(A)の俳句であると解釈して原句に近い英語Haikuに翻訳します。
hanazukare_
I dozed,
leaning against a person dozing
「weblio英和和英辞典」によると、「花疲れ」は「tiredness after cherry blossom watching」と英訳されています。
この英訳を用いると説明的な散文になり、Haikuの面白さが損なわれますが、構文などを工夫して次のように英語Haikuにしてみます。
I dozed,
leaning against a person dozing_
fatigue from cherry-blossom viewing
HAIKUらしく簡潔に翻訳するには、季語「花疲れ」は「寿司」(sushi)や「すき焼き」(sukiyaki)などと同じく、季語は日本固有・俳句特有のものとしてそのままローマ字の「hanazukare」にせざるを得ませんね。
ちなみに、原句が「眠る」と現在形の表現ですから、上記の英訳の「dozed」を「doze」と現在形にすると、「花疲れをすると、・・・眠る」と習慣的行為を句に詠んだことになります。
ご参考までに、上記(B)(C)の解釈に準じ試訳してみます。
(B)
hanazukare_
I dozed,
someone dozed leaning against me.
(C)
hanazukare_
a man dozed,
a woman dozed leaning against him.
英語は同じ言葉の反復をきらいますが、上記の翻訳では原句の面白さを反映するために敢えて同じ単語を繰り返しています。なお、personやman、womanなどは実態に合わせて適切な名詞を入れ替えて俳諧味を出すとよいでしょう。
原句の句意と異なるかも知れませんが、花見時によく見かける車内の光景として次のように英語HAIKUを作ってみます。
hanazukare_
couples of people doze in a train,
leaning agaist each other
この「花疲れ」の俳句の最後は「眠る」と現在形ですから、花見の疲れという現象の一面の真理を詠んだものと解釈して次のように翻訳して見ます。
hanazukare_
people tend to doze
leaning against one another
興味のある方は「バイリンガル俳句・HAIKUを楽しむ <高浜虚子の俳句「春の山」>」もご覧下さい。
国際俳句交流協会などの俳句愛好者によって進められています。
チュヌの主人は言語の壁を破るチャレンジをして、
日英バイリンガル俳句を楽しみながら、
草の根運動の一助になればとの思いで、
俳句やエッセイなどのブログを書いています。
ご意見やコメントなど、投稿して頂けると有難いです。
投稿して頂く場合には「コメントを投稿」(記事の最後の欄)に、
次の手順で入力して下さい。
(1)名前の欄に貴方の氏名を記入。
(2)メールアドレスの欄に貴方のメールアドレスを記入。
(3)最後の「投稿」ボタンをクリック。
(4)上記の結果表示されるセキュリティの検証テキストを指示通りに入力する。
なお、ご投稿頂いた内容はチュヌの主人の任意の裁量で
適宜公開させて頂きます。予めご了承ください。