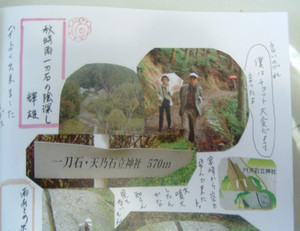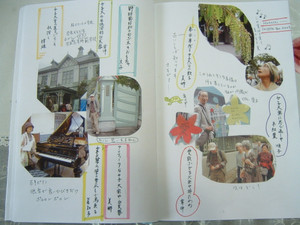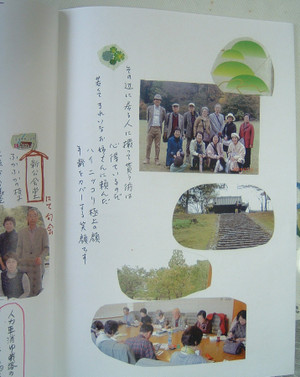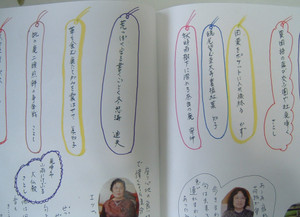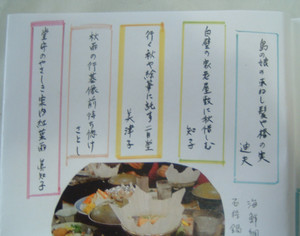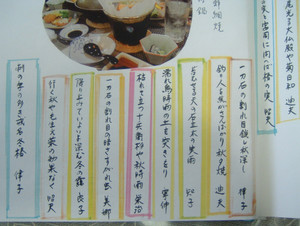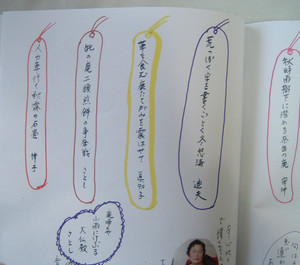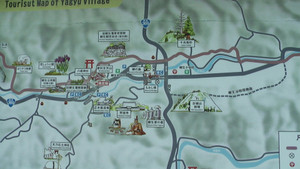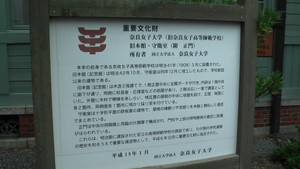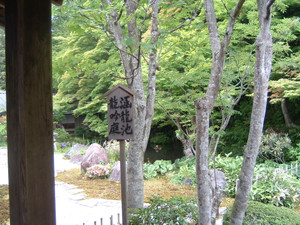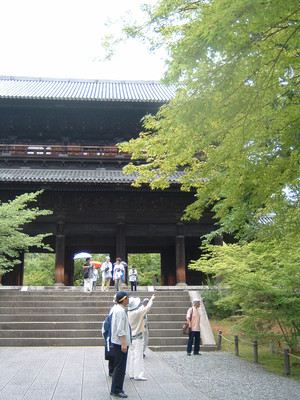(2025.1.18 更新)
去年今年宇宙は廻りめぐるかな
足らざるを補ひ合ひて去年今年
(薫風士)
虚子の俳句「去年今年貫く棒の如きもの」の棒とは何か?
「棒」は「虚子の信念」などの比喩でしょう。
(薫風士の新解釈)
著名な俳人の著書の関連部分のページの写真を掲載して、従来の解釈・通説を下記のとおり紹介させて頂きます。
(写真1&2) 夏井いつき著「俳句鑑賞の授業」(P178~179)


夏井いつきさんは、虚子のこの俳句を高く評価して、「『貫く棒の如きもの』という抽象的な比喩だけで、一瞬と永遠を合わせ持つ『去年今年』という季語の本質を見事に表現している」と述べていますが、夏井先生の「棒」を「一瞬と永遠の比喩」と解釈する考え方は腑に落ちません。
従来、この俳句の「去年今年」を「貫く棒の如きもの」の主語と解釈して、俳人や評論家などが様々な解説をしていますが、何れの解説も決め手になっていないと思います。
虚子は、1981年(昭和56年)7月17日に亡くなった水原秋桜子への追悼句「たとふれば独楽のはぢける如くなり」に於いて主語(秋櫻子と虚子との関係の在り様)を省略しているように、この「去年今年」の句においても、棒の主体を省略して去年今年を副詞として用いていると解釈すると、すっきり説明が出来ます。
虚子が「去年今年」を主語として俳句を作っていたとすれば、「独楽」の俳句と同じように助動詞「なり」を用いて、「去年今年貫く棒の如きなり」と表現していた筈でしょう?
助動詞「なり」を使わず、「もの」と表現したことは、「去年今年」が主語でないことの証だと思いませんか?
「去年今年」を「虚子の信念」との取合せである、すなわち、「棒」を「虚子の信念」と解釈する考え方は、まだ一般的に通説として普及していませんが、反論出来ない限り正しい解釈と言えると思います。
(写真3)
 伊藤柏翠著「虚子先生の思い出」(P96-97)
伊藤柏翠著「虚子先生の思い出」(P96-97)
高浜虚子は宗演禅師のもとで参禅弁道をしたとのことですが、「明け易や花鳥諷詠南無阿弥陀」と詠んでいますから、薫風士の新解釈を一概に的外れとは言えないでしょう。
(写真4) 金子兜太著「酒止めようか どの本能と遊ぼうか」P140-141

金子兜太も、去年今年の俳句について「観念臭が強い」と言ってあまり高い評価をせず、通説通り「一物仕立て」として解釈していますが、その解釈・評価に兜太の取巻きも同意しています。
(写真5)パソコンで読んだ現代俳句協会の記事の一画面

「去年今年」の「棒」を取合せとして、「男性器のメタファー」とも解釈できると、面白い解釈をしています。(評者横須賀洋子)
写真をタップ拡大して、記事をご覧下さい。
「きごさい歳時記」の解説によると、「去年今年」の季語の来歴は『毛吹草』(正保2年、1645年)にあります。
(青色の文字をタップすると関連のリンク記事をご覧になれます。)
お暇があれば、2015年作成の面白い下記のオリジナル記事をお楽しみ下さい。
高浜虚子の「去年今年」の俳句について、稲畑汀子さんは「虚子百句」において次のように述べている(抜粋)。
「昭和25年12月20日、虚子76歳の作である。
・・・(省略)・・・
去年と言い今年と言って人は時間に区切りをつける。しかしそれは棒で貫かれたように断とうと思っても断つことのできないものであると、時間の本質を棒というどこにでもある具体的なものを使って端的に喝破した凄味のある句であるが、もとよりこれは観念的な理屈を言っているのではない。禅的な把握なのである。体験に裏付けられた実践的な把握なのである。
・・・(省略)・・・

ところで棒とはなんであろう。この棒の、ぬっとした不気味なまでの実態感は一体どうしたことであろう。もしかすると虚子にも説明出来ず、ただ「棒」としかいいようがないのかも知れない。敢えて推測すれば、それは虚子自身かも知れないと私は思う。
この句は鎌倉駅の構内にしばらく掲げられていたが、たまたまそれを見た川端康成は背骨を電流が流れたような衝撃を受けたと言っている。感動した川端の随筆によって、この句は一躍有名となった。・・・(以下省略)」
稲畑汀子さんは上記の如く述べているが、川端康成はこの句の「棒」をどのように解釈したのだろうか?
「貫く棒の如きなり」と言わず、「貫く棒の如きもの」と言っているから、「棒」は「時のながれ」というよりも「虚子の信念」の比喩であると思う。
「虚子俳句の痴呆性」を云々する人がいるが、この「去年今年」の句には「大鐘のごとし。小さく叩けば小さく鳴り。大きく叩けば大きく鳴る。」という坂本龍馬の言(勝海舟に説明した西郷隆盛の評価)を当てはめたい。
文学に限らず、音楽や絵画など、芸術は自己実現の個性を表現するものであり、それをよく理解できるか否かは鑑賞する人の性格や人生観、能力などが左右する。まして、俳句は17文字(音)で表現する短詩であり、論理ではなく感性にうったえるものである。従って、俳句はその作者と「場」を共有するか、それが作られた「場」を適切に推定することが出来なければ理解できないことがある。
特にこの「去年今年」の句のように比喩的な俳句は、読む人の見方次第で卑しい句であると誤解されることもある。
その逆に、俳句が作者の意図以上によく解釈されることも珍しくない。
それは俳句の本質的な限界でもあり広がりの可能性でもある。
中立的な表現の俳句は鏡のように、読む人の心を映しだす。
虚子はこのような俳句の面白さもこの句に織り込んだのではなかろうか?
大岡信さんは「百人百句」において、「俳句という最小の詩型で、これだけ大きなものを表現できるのはすごいと思わざるを得なかった。」と次のように述べている(抜粋)。
「(省略)・・・昭和20年代後半から30年代にかけては『前衛俳句』の黄金時代で、若手の俳人はそちらに行ってしまい、虚子は一人さびしく取り残されている感があった。
・・・(省略)・・・私は現代詩を書いていたので、・・・(省略)・・・どちらかというとはじめに前衛派的な人々の句に親しんだので、それから逆に句を読み進め、高浜虚子を初めてというくらいに読んでみた。すぐに感じたのは、虚子の俳人としての人物の大きさだった。
私は常々現代詩を作り、・・・(省略)・・・斎藤茂吉が好きだったので茂吉の歌もよく読んでいた。しかし、『去年今年』の句を読んだときに、俳句という最小の詩型で、これだけ大きなものを表現できるのはすごいと思わざるを得なかった。・・・(以下省略)」
この句についてインターネットで検索していると、宗内敦氏の「アイデンティティ-第二芸術」というタイトルの傑作な記事があった。
「去年今年(こぞことし)とは、行く年来る年、時の流れの中で感慨込めて新年を言い表す言葉である。しかして虚子のこの一句、『貫く棒の如きもの』、即ち、時の流れを超えて『我ここにあり』と泰然自若の不動の自我を描いて、まさに巨星・高浜虚子の面目躍如たる『快作にして怪作』(大岡信『折々のうた』)の自画像である。
それが何としたこと、バブル絶頂の頃だったか、ある新聞の本句についての新春特集ページに、『この句を知ったとき、顔が火照り、胸がときめき、しばらくは止まらなかった』という中年婦人の感想文(投書)が載せられた。一体何を連想したのか。破廉恥にも、よくぞ出したり、よくぞ載せたりと、バブル時代の人心・文化の腐敗に妙な感動をもったことを思い出す。・・・(以下省略)」
この「中年婦人」を「破廉恥」とか「卑しい」などと決めつけるのは誤解かも知れない。
この女性は汀子さんの上記の「虚子自身かも知れない」というコメントと英語「itself」の俗語の意味とを自然に結び付けて連想したのかも知れないのである。
「虚子自身」も自分自身の「それ自身」を客観写生して、「生命力の強さ」をこの俳句で表現したのだ、と深読み出来ないこともない。
この句を作ったとき虚子は夏目漱石の「草枕」の冒頭にある有名な文「智に働けば角が立つ、情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」も意識していたかもしれない。
この句の「棒」のイメージは、「草枕」の「情に掉させば流される」という文句や方丈記の名文句、美空ひばりのヒット曲「川の流れのように」の歌詞など、時世・人生を表現するのに用いられる「川のながれ」とは全く異なり、力強くて斬新なものである。
虚子は「深は新なり」とか「古壺新酒」と言っている。「花鳥諷詠」と「客観写生」を唱道していたが、「前衛俳句」の黄金時代にあって、「去年今年」の句を作ることによって「これも『花鳥諷詠』だ」と、その幅の広さと虚子の信念と自信をアッピールすることを意識していたのではなかろうか。
青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。