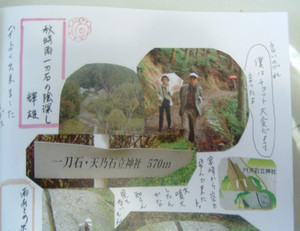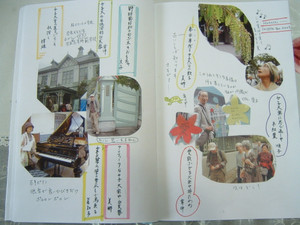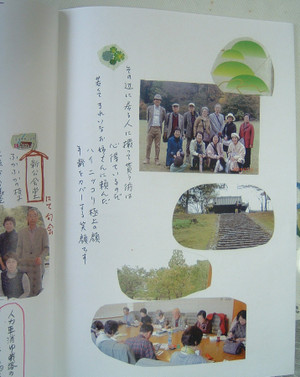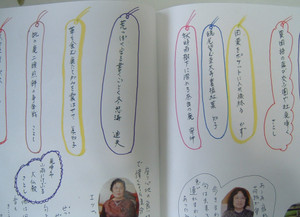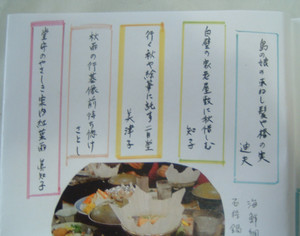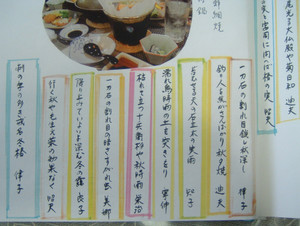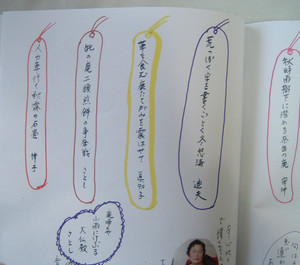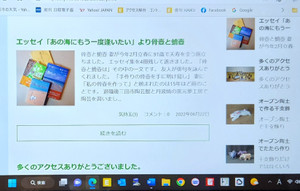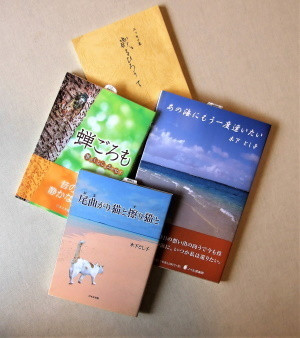本との出会い(5): 「俳句の宇宙」と「大悪人虚子」
「俳句の宇宙」(花神社1989年発行)において、長谷川櫂氏は虚子について次のように述べている。
「虚子を勉強していると、ときとき、不気味な虚子に出会う。久女の場合だけに限らない。虚子にとっては、俳句とホトトギス王国とどちらが大切だったのか。俳人だったのか、権力の亡者であったのか――そんな疑問が頭をもたげてくる。あまりにも現世的な姿の虚子。それはたいてい、暗くて大きくて、不敵な笑いを浮かべている。黒い虚子。こういう虚子はなかなか好きになれない。」(第三章2の最後から抜粋)
「しかし、俳人であったのか、権力の亡者であったのか、と二者択一で割り切れないところに虚子のほんとうの難しさ、面白さがあるのかもしれない。虚子のなかでは、よき俳句作家と冷酷な権力者とが、ただ表面上だけでなく、深いところで融合しているのではないだろうか。俳句と「力」とが――といいかえてもいい。「力」という要素は虚子の俳句や俳句観に深く埋め込まれている。虚子の俳句は「力」の表現だともいえると思う。虚子の奥底にあって、磁力を発しつづける「力」。これが17文字の俳句になったとき、図太いとも、また、艶やかとも映るのではないか。」(第三章3の冒頭から抜粋)
「虚子は、みずから「大悪人」を名のる。この句(「初空や大悪人虚子の頭上に」)は一見、大謙遜に見えながら、実は大うぬぼれの句であるらしい。自分の「力」への揺るぎない自信。虚子は、この句でも不敵に笑っている。」(第三章3の最後抜粋)
「微粒子の世界から星たちの空間まで、響きわたる巨大なオーケストラとしての宇宙。小さな草の芽を見ながら、目の前に湧き起こりつつある宇宙の音を、はっきりと感じとっている虚子。こういう虚子はいちばん興味深い虚子だ。同時に手怖い虚子である。」(第三章5の終わり抜粋)
「昭和22年頃、虚子の言葉というのが私の耳にもとどいた――「第二芸術」といわれて俳人たちが憤慨しているが、自分らが始めたころは世間で俳句を芸術だと思っているものはいなかった。せいぜい第二十芸術くらいのところか。十八級特進したんだから結構じゃないか。戦争中、文学報国会の京都集会での傍若無人の態度を思い出し、虚子とはいよいよ不敵な人物だと思った。」(注:『第二芸術』の「まえがき」)(第三章6の終わりより抜粋)
「傍若無人の態度」とは具体的には何を指しているのだろうか? 虚子はこの時期にどんな俳句を作っていたのだろうか?
「俳句の宇宙」からの上記抜粋にあるような虚子の「力」は何から出ているのだろうか?
花鳥諷詠の「極楽の文学」としての俳句を世に広めたいという信念の強さが「力」となったに違いない。
そういう信念が、「花鳥諷詠南無阿弥陀仏」や「天の川の下に天智天皇と臣虚子と」「初空や大悪人虚子の頭上に」「去年今年貫く棒の如きもの」などの俳句に結実したのものと思うが、虚子がこれらの句を作った「場」を知りたい。
「高浜虚子の世界」(角川学芸出版「俳句」編集部)のアンケート「私の虚子」③「いま、虚子について思うこと」に対して、俳文学者矢羽勝幸氏は次のように回答している。(抜粋)
「③ 碧梧桐の方向も近代化の過程で当然だとは思うが、虚子のとった“九百九十九人のみち”すなわち俳句が庶民文芸であることを(芭蕉の軽み、一茶の最後にめざした俳諧)近代に再生、継承した功績は偉大だと思う。“九百九十九人のみち”を凡人主義と解してはならない。・・・(以下省略)」
また、大木あまり氏(俳人)はアンケート②「心にのこる虚子の言葉、あるいは愛読の虚子著作」に対して、次のように回答している。
「② 理論の花より芸の花こそよけれ。標語の花よりも真の実こそよけれ。」
「世評を気にかけないで行動する人は快い。私はそういう人を好む。世評を気にかけて行動する人はみじめだ。私はそういう人を好まない。」
「高遠なる思想を辿る事もよいが、また平凡な日常に処する事も大事だ。」
坊城俊樹さんは「虚子の100句を読む」において、虚子の句「石ころも露けきものの一つかな」を挙げて次のように述べている(抜粋)。
「・・・(省略)・・・むしろ年尾は『客観写生』『花鳥諷詠』提唱後の虚子の句でも、表現的に単なる写生句より、自然界にあるすべての有情のものとして、人間を含めた、大きな句を取り上げて言っている。年尾の好みと言っていい。筆者もまた、この句に関してはそのように感じる者であるが、虚子はそれをあくまで『月並』的な鑑賞であるとした。
しかし、虚子の謂う『天地有情』という観点からも、この句は現代の伝統派がよく使う、通俗的で安っぽい措辞の『の心あり』『といふ命あり』などとは根本的に異なる広遠な句と思うのだが。
この句をあえて取り上げたのも、大震災の現場にある石ころの映像を見たからである。その被災地にある石ころは只の石ころではない。甚大な被害と、多くの被災者の命を奪った大地にころがっていた石ころである。この句を思い出さずにはいられなくなる石ころであった。」
上記のように、俊樹さんは東日本大震災に言及しているが、この句を虚子が作ったのは昭和4年(1929年)の8月であり、その前の6月には北海道駒ヶ岳が噴火して死傷者も若干出ていたようである。今年は木曽の御嶽山が噴火して多くの死傷者が出た。
虚子はこの「石ころ」の句を作ったとき、駒ヶ岳の噴火を意識していたのだろうか?
1923年に起きた関東大震災について、河東碧梧桐は俳句を作っているが、虚子は一切俳句を作っていないとのことである。
「虚子は俳句など短詩にはそれぞれサイズに応じた適所持分があるとしており、後に起こった太平洋戦争や原子爆弾についても俳句を詠んでいません。また、震災忌、敗戦忌、原爆忌を季語として認めていなかった」そうである。
いずれにせよ、虚子は、心の糧になる花鳥諷詠の文学、すなわち「極楽の文学」としての俳句、を大衆に広めることを目指していたのだから第二芸術という批判は的外れとして、「俳句も第二芸術まで来ましたか」「十八級特進したんだから結構じゃないか」と議論の対象にしなかったのだろう。
虚子は、昭和18年に出版した「俳談」の序文に、
「何故に何という理屈を述べることはさけて、只何々であるという断定した意見だけを述べたというようなものである。善解する人は善解してくれるであろうと思う。」と述べ、さらに、
「本ものの虚子で推し通す」というタイトルで次のように述べている。
「自分は自分の固く信ずるところがあり、この信仰は何人もどうすることも出来ないものである。他の刀が切っても切ることは出来ぬ、他人の舌が千転してもどうすることも出来ぬものである、ということを固く信じている。従来俳壇に在って、私ほど多くの人々から攻撃されたものも少ないであろうと思う。・・・ 省略・・・自分の俳句は、少しもそれらの言葉に累せらるることなしに、著々として歩を進めているということを、固く信じているのである。」
「天地有情」といえば土井晩翠の詩が有名であるが、このような詩は誰でも簡単に作れるわけではない。俳句は庶民が手軽に楽しむのに適した世界最短の型式詩といえる。これを高邁な文学としてのみ追求すれば一部の専門的俳人しか作れなくなる。虚子は元々俳句の良さ・特質や限界を認識した上で花鳥諷詠の楽しさを大衆に教えることを考えていたのだろう。
善悪のとらえ方や価値観は時代とともに変化する。虚子は悠久の宇宙の森羅万象・人間も含む自然・花鳥諷月を俳句にすることの可能性と限界を喝破していたに違いない。
だから、親子ほど歳の違うフランスかぶれの桑原武夫に第二芸術と言われようと、青臭い議論としてそれに頓着しなかったのだろう。
虚子自身も駄句と批判される句を作っている。虚子が意図したわけではないだろうが、それが結果として俳句を親しみやすい庶民の文芸・娯楽にして今日の俳句の隆盛をもたらしているとも言えるのではなかろうか。
現在の高齢化社会で多くの人々が俳句を趣味として老後をエンジョイしている。そのことを知れば、虚子は「傲岸と人見るままに老の春」という俳句を作ったように、大悪人と言われようと自分の選んだ途は間違いでなかった、とニッコリするのではないか。
ちなみに、インターネット検索したところ、「傲岸に人見るままに老の春」というのもある。
「に」と「と」では主客逆転した句意の解釈が成り立つ。「に」はミスタイプと思うが、この句は虚子が人を傲岸な態度で見ていることを意味するのか、人が虚子を「傲岸だ」と見ていることを意味するのか、どちらが正しいのだろうか?
「君、そんなことは超越していたよ。何事も『色即是空』だ。」という虚子の声が聞こえるような気がする。
青色文字をタップすると、最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。
トップ欄か、この「俳句HAIKU」をタップすると、最新の全ての記事(タイトル)が表示されます。記事のタイトルをタップ(クリック)して、ご覧下さい。