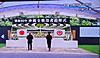俳句 365 haiku (184) 《牡丹1 Bashō》
牡丹蘂ふかく分出る蜂の名残哉
(botan-shibe fukaku-wakeizuru hachi-no-nagori-kana)
(芭蕉)
sorrow of parting,
bee’s pushing its way
out of botan-shibe;
(Translated by Lovee)
(Note)
Bashō composed this haiku for appreciation of hearty hospitality to him when he visited his disciple.
Thus, the bee implies Bashō and the botan-shibe, which means stamen or pistil of peony, is a metaphor of his disciple.